
能登半島地震のニュースを見たとき、胸の奥がぎゅっと痛みました。
倒れた家屋や、避難所で寄り添う人たちの姿を見ながら、ふと自分の暮らす中山間地を思い浮かべたんです。
山に囲まれ、道も細く、避難に時間がかかるこの地域。
もし同じような地震が起きたら、きっとすぐには助けが来ない。
その現実を想像した瞬間、「自分にも何かできる知識を身につけなければ」と思いました。
それが、防災士を志すきっかけでした。
防災は「誰かがやってくれること」ではなかった
それまでの私は、防災に対して「行政や専門家がやってくれること」という意識が強かったように思います。
避難訓練も、どこか“決まりごと”のように感じていました。
けれど、被災地のニュースを見続けるうちに、
「助け合いの力」や「地域での連携」がどれほど大切かを痛感しました。
道路が寸断され、外部からの支援が届くまで時間がかかる中、
最初の数日を支えるのは、結局“その土地に住む人たち”なんですよね。
「知っているだけで救える命がある」
そうした現実を知ってから、「自分にもできることを学ぼう」と思い、防災士の勉強を始めました。
テキストを開くと、まず驚いたのは「想像していたよりも、日常生活に近い内容」だったことです。
たとえば――
・家具の固定や非常持ち出し袋の準備
・地域の危険箇所を家族で確認しておく
・災害時に家族が離れた場合の連絡手段を決めておく
こうした“身近な行動”こそが、被害を減らすための第一歩。
知っているか知らないかで、守れる命の数が変わることを学びました。
そして何より、「知識があると心が落ち着く」という感覚を実感しました。
備えを意識するようになってから、ニュースを見ても“ただ不安になる”のではなく、
「自分ならどう行動するか」を考えられるようになったんです。
小さな気づきが、行動の力になる
防災士の学びを通して感じたのは、
防災とは「誰かに任せること」ではなく、「一人ひとりができる範囲で備えること」だということ。
たとえば、家族の中で避難場所を話し合うだけでも立派な防災です。
地域で声を掛け合うだけでも、大きな安心につながります。
そんな“日常の延長にある備え”を、これからも伝えていきたいと思っています。
今日からできる、優しさのかたち
防災士を目指したのは、特別な使命感からではなく、
「自分の大切な人を守りたい」という素朴な気持ちからでした。
でも、その小さな気づきが、学びのきっかけになり、行動する力にもなりました。
そして今では、「自分が学んだことを、誰かに伝えること」も大切な備えのひとつだと感じています。
防災は、いつかの“もしも”ではなく、
**今日から始められる“優しさの形”**なのかもしれません。
🌱
あなたのまわりの大切な人を守るために、
今日、ほんの少しの「備え」を考えてみませんか?

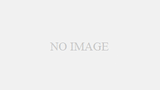
コメント