
「防災」って聞くと、ちょっと大げさに感じることがありますよね。
でも実は、毎日の暮らしの中で少し意識を変えるだけで、立派な備えになります。
ここでは、家族みんなで楽しみながら取り組める“防災小ネタ”を集めてみました。

① 家族みんなの「防災LINEグループ」
災害時にあわてないよう、家族専用のグループを作っておきましょう。
スタンプ一つで安否確認できるルールを決めておくと、いざという時も安心です。
ただ災害時は、すぐにスマホが繋がらない場合も想定されるので、オフラインでも確認できる方法も検討しておくと安心です。
また携帯キャリアによっては、通信衛星(スターリンク)を使用できるものもありますので、場合によってはご検討してみてはいかがでしょうか。
↓
au Starlink Direct (au/UQ mobileの提供するサービスです)
② お風呂のお湯はすぐ抜かない
お風呂のお湯は、断水時に使える大切な“生活用水”。
「寝るまでは残しておく」を家族ルールにしておくと、困ったときの助けになります。
防災以外にも、残り湯は洗濯や植物の水やりなどにも使えるので、日常の節水にもなりますよ。
③ 週末「防災ピクニック」
非常食を外で食べてみるだけでも立派な訓練。
味や使い方を試しながら、「これなら子どもも食べられるね」と話す時間を楽しみましょう。
④ 家族で「停電ごっこ」をしてみる
夜にあえて電気を消して過ごしてみると、見えてくることがたくさんあります。
ランタンを囲んで過ごす時間は、ちょっとしたキャンプ気分にもなりますよ。
⑤ 「食べて備える」ローリングストック
非常食を“非常時専用”にしないことがコツ。
普段の食事で少しずつ使いながら、新しいものを補充していく仕組みづくりを。
また、普段食べ慣れているレトルト食品を、ちょっと多めに買っておくのも備える際のコツ。食べ慣れている味なので、いざと言う時にも不安無く食べられます。
ただし非常時には調理法が限られる場合もあるので、代わりの調理手段も準備しておきましょう(カセットコンロ等)
⑥ 家族写真を1枚、防災リュックに
もしもの時に役立つだけでなく、「家族を守ろう」という気持ちを再確認できます。
思い出の1枚を入れておくだけで、心の支えにもなります。
⑦ 地域の「避難場所探し散歩」
週末の散歩で避難所まで歩いてみましょう。
「こっちの道は広いね」「ここは暗いかも」と話すだけでも、防災意識が自然に高まります。
その際には、自治体が作成しているハザードマップを見ながら歩いてみましょう。普段使っている道が、実は危険が潜んでいるかも…なんて発見も。
ハザードマップは、自治体のHPでも確認出来るので、スマホで見ながらなんて活用も出来ますよ。
⑧ 子どもとつくる「マイ避難バッグ」
子どもが自分で選んだお気に入りグッズを入れると、避難時の安心感につながります。
“自分を守る力”を育てる第一歩に。
その時は、大人も一緒にマイ避難バッグを作りましょう。
みんなが何を入れているかが分かると安心です。
⑨ 家族の「連絡カード」を冷蔵庫に
電話番号・避難場所・集合場所を1枚にまとめて貼っておきましょう。
誰でもすぐ見られる場所にあることが大切です。
例えば冷蔵庫、玄関のシューズボックス等、全員が目に入れられる位置を家族で決めておきましょう。
おわりに
「防災」は“準備する日”を特別に設けなくても、
“毎日の中でちょっと意識する”ことから始められます。
子どもと笑いながら、防災バッグをのぞいてみる。
非常食を試しながら、「これ、けっこうおいしいね」と話す。
そんな日常の積み重ねこそが、いざという時に家族を守る力になります。

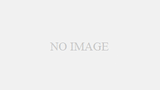
コメント