
地震や台風のニュースを見るたびに、
「うちの地域は大丈夫かな…?」と心配になることがあります。
それでも、日々の忙しさに追われていると、
備えのことって、つい後回しになってしまうものですよね。
私もかつてはそうでした。
けれど、能登半島地震の映像を見たとき、
「もし自分の住むまちで同じことが起きたら…?」
そんな不安が胸に残って離れませんでした。
防災士という資格を知って
きっかけは「自分が動けるようになりたい」という想い
その時、「誰かを待つより、自分が動けるようになりたい」と思い、
防災士という資格を知りました。
防災士は、地域や職場、家庭などで防災の知識を広め、
災害時に冷静に行動できるよう支援する“防災の伝え手”のような存在です。
全国で20万人以上の防災士が活動していて、
その多くは特別な専門職ではなく、
会社員や主婦、学生など、わたしたちと同じ「身近な人たち」です。
より詳しい活動内容や資格取得の流れは、
👉 日本防災士会 公式サイトhttps://www.bousaishikai.jp/
で紹介されています。興味のある方は、ぜひ一度のぞいてみてください。
私の住んでいる市町村では、行政主催の防災士育成講座(名称は市町村により異なります)が開催されていたので、そちらを受講して資格を取得しました。取得にかかる費用や期間は、取得する方法によっても異なりますので、気になる方は日本防災士会公式サイトや、お住いの市町村の担当部署にお尋ねください。
共に頑張る仲間も見つけられて、活動のモチベーションも上がりますよっ!
学びの中で気づいたこと
「知識」だけじゃなく「つながり」が大切
防災士の講座では、地震や水害、火災の基礎知識はもちろん、
避難所の運営訓練や、被災地支援の実際も学びます。
思っていた以上に「人とのつながり」が大切で、
“知識だけでなく、行動力や思いやり”が問われる資格だと感じました。
仲間とともに学び合う時間
資格を取ってからは、地域の防災イベントに参加したり、
防災研究会で仲間と情報を共有したりしています。
ときには市のイベントでスタッフとしてお手伝いすることもあり、
「聞いてよかった」「役に立ちました」と声をかけてもらえると、
小さな一歩でも、誰かの安心につながるんだと感じます。
暮らしの中に“やさしい防災”を
防災は、特別な人のものじゃない
防災士になって気づいたのは、
防災は“特別な人だけがやること”ではないということです。
誰にでもできることがあり、
その積み重ねが、まち全体の安心につながっていく。
今日からできる、小さな一歩
たとえば、家族と避難経路を話してみること。
非常食の賞味期限を確認すること。
それも立派な“防災活動”のひとつです。
今日の小さな行動が、未来の「ありがとう」につながる。
そんな気持ちで、これからも暮らしの中に
“やさしい防災”を取り入れていけたらと思います。
おわりに
防災士という資格を通して感じるのは、
「守りたい」という想いが、
まちを少しずつ優しく変えていく力になるということ。
むずかしいことはできなくても、
自分にできることから始めればいい。
それが、わたしの思う“やさしい防災”の第一歩です。
🌿 この記事を読んで、「防災士ってどんな活動をしているの?」と興味を持ってもらえたら嬉しいです。
次回は、防災研究会での実際の取り組みやイベントの様子をご紹介します。

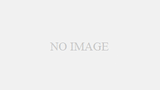
コメント